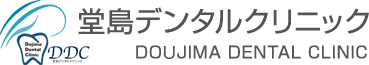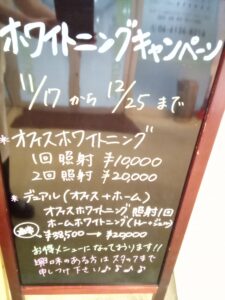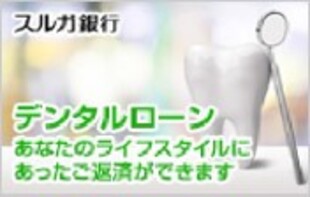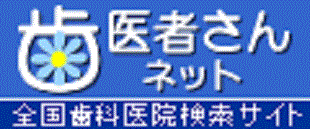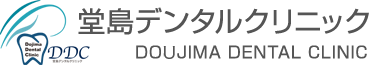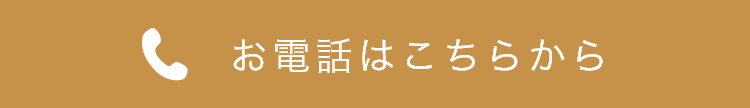歯医者の麻酔の種類は?食事を摂るタイミングや麻酔を受けるときの注意点を解説

歯医者の治療では、麻酔が使われることがあります。
中には麻酔注射の痛みが怖い方や麻酔の感覚が苦手という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、歯医者で行われる麻酔法について詳しく解説します。
麻酔の持続時間の目安や麻酔を受けるときの注意点などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
歯医者で行われる麻酔方法

麻酔薬には『局所麻酔薬』と『血管収縮薬』の2種類があり、それぞれの特徴は以下の通りとなっています。
- 局所麻酔薬:安全性が高く、アレルギー反応を起こす心配がほとんどない
- 血管収縮薬:麻酔の効きを良くして持続期間を長くする効果がある
歯医者で使われる麻酔薬には、上記の両方が配合されていることが多いです。
また歯医者で行われる麻酔方法は大きく分けて3つの方法があります。
- 局所麻酔法
- 精神鎮静法
- 全身麻酔法
ここでは上記3つの麻酔方法についてそれぞれ解説します。
局所麻酔法
局所麻酔法は、歯医者でもっとも一般的に用いられているオーソドックスな麻酔方法です。
局所麻酔法には3つの種類があります。
- 表面麻酔法
- 浸潤麻酔法
- 伝達麻酔法
ここではそれぞれの特徴を見てみましょう。
表面麻酔法
表面麻酔法は、歯茎の表面に麻酔薬を塗布する局所麻酔方法です。
歯茎の表面の感覚を麻痺させるための麻酔のため、歯自体を麻酔するためには浸潤麻酔法や伝達麻酔法などの注射による麻酔が必要になります。
しかし表面麻酔で歯茎の表面を麻痺させることにより、注射を刺すときの痛みを軽減させることができます。
浸潤麻酔法
浸潤麻酔法は、歯の周囲の歯茎に注射する局所麻酔法です。
虫歯の治療から親知らずの抜歯まで、幅広い治療に用いられています。
歯茎に針を刺すときに痛みを感じますが、前述の表面麻酔法と組み合わせたり麻酔薬の温度管理に気を配ったりすることにより、痛みを軽減することが可能です。
また最近は細くて切れの良い針が開発され、以前よりも痛みを抑えて麻酔ができるようになっています。
伝達麻酔法
伝達麻酔法は、太い神経の幹に注射することで、唇や舌を含めた広範囲に麻酔を作用させる局所麻酔方法です。
下顎の奥歯など、麻酔が比較的効きにくい部分を治療する際に用いられます。
麻酔効果が長時間続くため、治療後の痛みが気になりづらく、鎮痛薬の量を減らせるメリットがあります。
精神鎮静法
精神鎮静法は、不安や恐怖心を和らげる麻酔方法です。
精神鎮静法には2つの種類があります。
- 静脈内鎮静法
- 吸入鎮静法
ここではそれぞれの特徴を見てみましょう。
静脈内鎮静法
静脈内鎮静法は、鎮静薬を静脈に点滴する麻酔方法です。
鎮静薬を静脈に点滴することにより、半分眠っているような状態を作り、患者さんの不安や恐怖心を和らげられます。
苦痛を感じないうちに治療が終わるため、歯科治療が嫌いな方や歯科治療中に具合が悪くなってしまう方に適しているでしょう。
またインプラント手術に用いられることが多い麻酔方法の一つでもあります。
吸入鎮静法
吸入鎮静法は、鎮静・睡眠・鎮痛作用を持つ笑気ガスを鼻から吸入する麻酔方法です。
不安感や恐怖感が取り除かれ、リラックスした状態で治療を受けることができます。
呼吸器や循環器、肝臓、腎臓などの重要臓器に対する作用が極めて小さいのも特徴です。
歯科治療に対し強い恐怖心を持っている方や小さなお子さんの治療などに用いられることが多い麻酔方法となっています。
全身麻酔法
全身麻酔法は、患者さんの意識を消失させて全身の感覚を麻痺させる麻酔方法です。
一般的な歯科治療では局所麻酔法または精神鎮静法による麻酔が行われますが、極度の歯科恐怖症を持つ方など意識がある状態での治療が難しい場合は全身麻酔法が用いられます。
3つの麻酔方法の中でも最も強い麻酔効果を持つ方法ですが、全身に麻酔が作用する分、以下のようなリスクも伴います。
- アレルギー反応
- 呼吸困難
- 循環器の問題
また全身麻酔はすべての歯科医院で行えるわけでなく、歯科大学病院や医科大学病院などの十分な設備が整っているところでないと行えません。
歯医者の麻酔で痛みを感じる理由

歯医者の麻酔で痛みを感じる理由は主に3つ挙げられます。
- 針を刺すときの痛み
- 麻酔液の圧力による痛み
- 個人の痛みの感じ方によるもの
ここでは上記3つの理由についてそれぞれ解説します。
針を刺すときの痛み
浸潤麻酔法や伝達麻酔法などの注射針を使う麻酔法の場合、針を刺す際に痛みが生じます。
特に歯茎や粘膜には多くの神経が通っているため、痛みを感じやすいです。
麻酔液の圧力による痛み
注射により麻酔液を注入する際、圧力によって組織が圧迫され、痛みが生じることがあります。
麻酔を注射する部分が炎症を起こしていたり骨が近い部分だったりすると、痛みを感じやすい傾向にあります。
麻酔液の圧力による痛みを低減するためには、少しずつ弱い力で麻酔液を注入する技術が必要です。
クリニックによっては、麻酔液の注入速度をコンピューターでコントロールできる電動麻酔注射を使用して痛みを軽減している場合もあります。
個人の痛みの感じ方によるもの
麻酔は同じ打ち方をしても、人によって痛みの感じ方に違いがあります。麻酔が全く痛くない場合もあれば、強く痛みを感じる場合もあるのです。
また精神的な緊張や不安が強まると、痛みを強く感じやすくなります。
麻酔の持続時間の目安

麻酔方法によって麻酔の持続時間が異なります。
ここでは局所麻酔法、精神鎮静法、全身麻酔法のそれぞれの持続時間の目安について解説します。
局所麻酔法
局所麻酔法は短くて10分、長くて6時間程度効果が持続します。
- 表面麻酔法:10~20分
- 浸潤麻酔法:2~3時間
- 伝達麻酔法:4~6時間
上記の時間が目安となりますが、麻酔の本数や個人差によって持続時間がさらに長くなったり短くなったりすることがあります。
また局所麻酔にはスキャンドネストという麻酔薬があり、これには血管収縮薬が含まれていないため、20~30分程度で効果が切れます。
いずれの方法においても、麻酔が切れるまでは食事を控えるようにしましょう。
精神鎮静法
精神鎮静法は笑気ガスの場合、30分から1時間程度効果が持続します。
吸入終了後は意識がしっかり戻るまで数分〜15分ほど安静にしなくてはいけないケースが多いです。
静脈内鎮静法の場合は麻酔が効いている間は記憶がほぼないくらいウトウトとします。治療終了後30分〜1時間ほど安静が必要です。
全身麻酔法
全身麻酔の持続時間は数時間程度です。
一般的に全身麻酔は入院施設がある病院で行われ、治療後1日入院してから帰宅することになります。
簡単な手術などの場合は、入院せず日帰りで治療できる場合もあります。
歯医者で麻酔を受けるときの注意点

歯医者で麻酔を受けるときの注意点は5つ挙げられます。
- リラックスして麻酔を受ける
- 食事は事前に済ませておく
- 全身の病気に注意する
- 飲酒・服薬に注意する
- 麻酔が切れるまでは食事を控える
ここでは上記5つの注意点についてそれぞれ解説します。
リラックスして麻酔を受ける
歯医者で麻酔を受けるときは、リラックスすることが大切です。
緊張や不安が高まると、麻酔が効きにくくなったり痛みを感じやすくなったりするだけでなく、稀にショックなどを起こすことがあります。
そのため治療前にリラックスできる方法を見つけておきましょう。具体的には深呼吸をしたり好きな音楽を聴いたりする方法が挙げられます。
また歯科医に不安点や恐怖心を伝えておくことで、親身になって対応してくれ、安心感を得ることができます。
食事は事前に済ませておく
歯医者で麻酔を受ける際は、食事を事前に済ませておきましょう。
麻酔の種類にもよりますが、治療部位周辺に注射による麻酔をした後は2~6時間程度、治療部位周辺や口内の感覚がなくなります。
基本的に麻酔が切れてからでないと食事ができないため、治療前に十分に栄養補給をしておくことが大切です。
全身の病気に注意する
歯医者で麻酔を受ける際は、全身の病気に注意が必要です。
特に持病がある場合や現在服用している薬がある場合は、事前に歯科医にきちんと伝えておきましょう。
血管収縮薬が含まれる麻酔薬は、高血圧、糖尿病、甲状腺機能亢進症などの持病をお持ちの方には適さないため、他の麻酔薬を使用する必要があります。
また持病がない方でも、当日の体調が悪い場合は麻酔の種類や量を検討し直す必要があるため、正直に伝えることが大切です。
飲酒・服薬に注意する
歯医者での麻酔では、飲酒や服薬にも注意が必要です。
これらは肝臓の機能に影響を与えるもので、麻酔薬が体内で長時間分解されず残ってしまう恐れがあります。
飲酒や服薬をする習慣のある方は、あらかじめ医師に伝えておきましょう。
麻酔が切れるまでは食事を控える
麻酔が切れるまでは食事を控えることも重要なポイントです。歯医者での麻酔は注射してから2~6時間程度効果が持続します。
その間治療部位周辺や口内の感覚がなくなるため、その間に飲食をすると唇や舌を噛んでしまうリスクがあるのです。
また麻酔が効いている間は温度も感じづらくなるため、やけどのリスクを避けるためにも熱いものは飲まないようにしましょう。
麻酔の効果が切れたら食事をしても良いですが、感覚が完全に戻るまではあまり噛まずに済むような柔らかめの食べ物を選ぶことをおすすめします。
歯医者の麻酔に関するよくある質問

歯医者の麻酔に関するよくある質問をまとめました。
- 妊娠中・授乳中でも麻酔は受けられる?
- 麻酔が痛くない歯医者はある?
- 歯医者の麻酔に副作用はある?
ここでは上記3つの質問についてそれぞれ解説します。
妊娠中・授乳中でも麻酔は受けられる?
妊娠中や授乳中の方でも、麻酔を受けることは可能です。
麻酔液は肝臓で分解されて胎盤を通過せずそのまま尿として排出されるため、赤ちゃんへの影響はありません。
しかし歯の痛みやストレスが母体に悪影響を及ぼし、間接的に赤ちゃんに影響が及ぶ可能性もあるため、妊娠中・授乳中の方は現在の状態をあらかじめ医師に伝えておくと良いでしょう。
麻酔が痛くない歯医者はある?
麻酔そのものの痛みを低減するよう配慮している歯医者はあります。
麻酔の痛みを低減する具体的な方法としては、以下のような方法が挙げられるでしょう。
- 麻酔注射の前に表面麻酔を行う
- 痛みの小さな針を使う
- 少しずつ弱い力で麻酔液を注入する
- 電動麻酔注射を使用する
痛みに配慮している歯医者の中には『無痛治療』を掲げているところもあるため、麻酔の痛みが不安な方はそのような歯医者を選ぶと良いでしょう。
歯医者の麻酔に副作用はある?
歯医者の麻酔の副作用は以下の通りです。
| 表面麻酔 | むくみ、じんましん、めまい、眠気、不安感、興奮、嘔吐など |
|---|---|
| 浸潤麻酔 | 血圧上昇、動悸、悪心、吐き気、手足の震え、痺れなど |
| 伝達麻酔 | 血圧上昇、動悸、悪心、吐き気、手足の震え、痺れなど |
| 静脈内鎮静法 | 血圧や呼吸への影響、アレルギー症状など |
| 吸入鎮静法 | 吐き気、下肢の脱力感など |
| 全身麻酔 | 吐き気、嘔吐、頭痛、のどの痛み、声がかすれる、歯の損傷、唇の傷・腫れ、寒気・発熱、喉の渇きなど |
上記のような副作用が現れた場合、すぐに医師に相談することが大切です。
まとめ
歯医者で行われる麻酔方法は局所麻酔法、精神鎮静法、全身麻酔法の3種類です。
一般的に用いられる麻酔の種類は浸潤麻酔法ですが、痛みを軽減させるために表面麻酔と併用する場合もあります。
麻酔の持続時間の目安は2~6時間程度で、麻酔の種類や体質により個人差があります。
歯医者で麻酔を受けるときは、リラックスして麻酔を受けること、食事は事前に済ませておくこと、麻酔が切れるまでは食事をしないことなどを心がけましょう。
堂島デンタルクリニックでは、虫歯や歯周病の治療はもちろん、審美修復や矯正治療なども行っています。
ネットからの初診予約にも対応しているため、ぜひ気軽にご相談ください。